食品添加物の知られざる危険性:あなたの食卓に潜む「毒」の正体
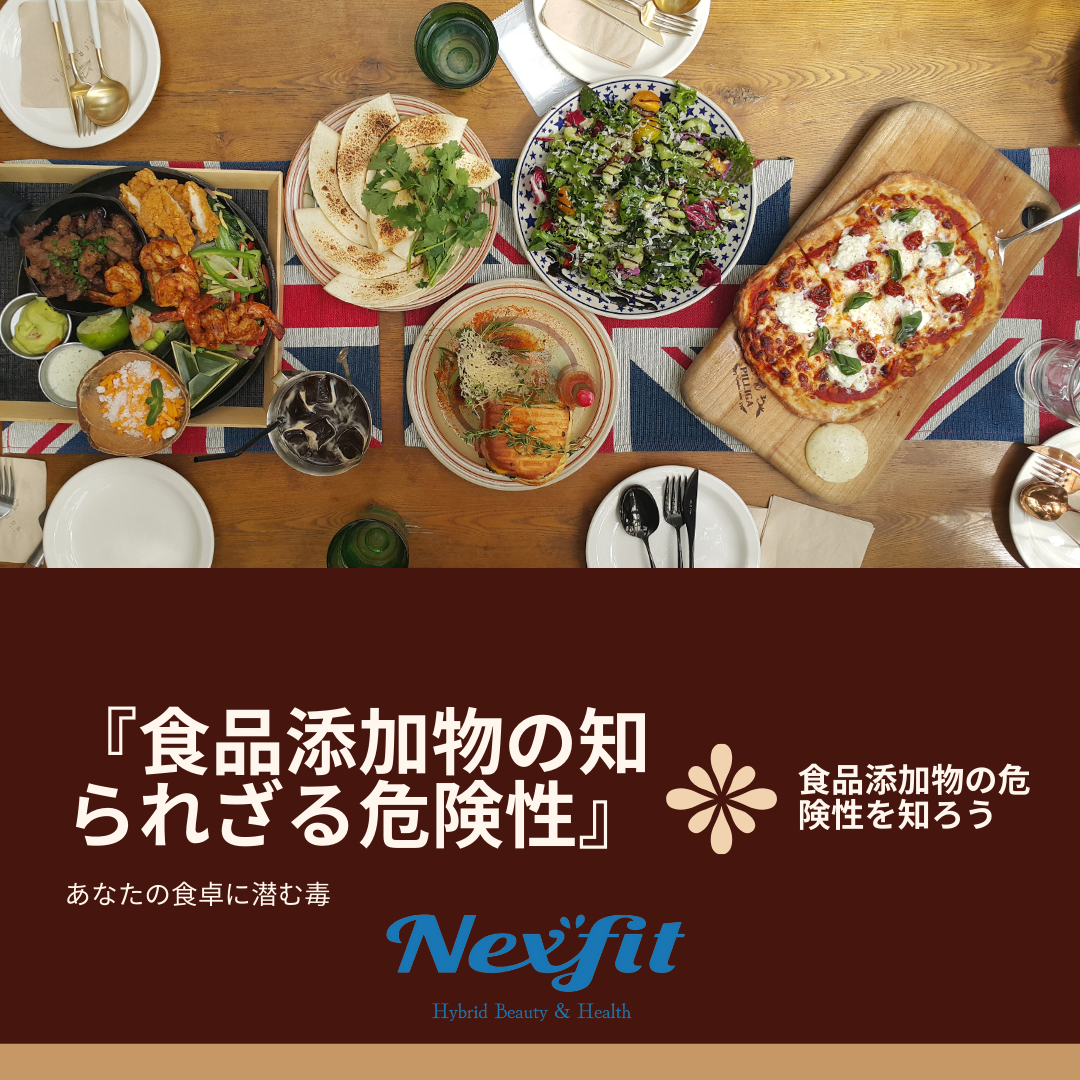
私たちは日々の食事を通して、体、心、そして魂の健康を育んでいます。しかし、現代の日本には、私たちの健康を蝕む「毒」が蔓延しており、その最たるものが食品添加物です。
「四毒」と「五悪」:食の危険性を示す新たな視点
吉野敏明の提唱では、食品の危険性を「四毒(しどく)」と「五悪(ごあく)」という独自のフレームワークで解説しています。
- 四毒: 小麦、植物油、乳製品、甘いもの。これらは、食品添加物よりもはるかに病気を引き起こす主要な要因であると指摘されています。
- 五悪: 食品添加物、農薬、化学肥料、除草剤、遺伝子組み換え食品。
このフレームワークにおいて、食品添加物は「五悪」の筆頭であり、私たちの健康に深刻な影響を与えています。
〈日本における食品添加物の特殊な状況〉
驚くべきことに、アメリカやヨーロッパ諸国、さらには中国でさえもがん患者が減少傾向にある中、日本だけががん患者の数が激増しています。この原因として、日本独自の食品添加物の規制緩和と消費習慣が挙げられています。
- 戦後の食料政策: 日本は第二次世界大戦後、アメリカの余剰食料(小麦、植物油、脱脂粉乳など)を大量に輸入し、消費を義務付けられました。これを強制的に消費させるため、「フライパン運動」や「牛乳運動」といった食料転換政策が推進され、パンや牛乳、揚げ物などの食事が奨励されました。
- 国際的な不平等条約: 日本はPL480条やMSA条約といった不平等条約により、アメリカの小麦や油などを買い続け、消費し続けなければならない状況にあります。
〈食品添加物の具体的な危険性とそのメカニズム〉
食品添加物は、がんや自己免疫疾患の増加に直接的に関係しています。
- がんの激増: この40年間でがん患者は3.8倍、大腸がんは7倍、肺がんは7倍、乳がんは5倍にも増加しています。
- 自己免疫疾患の増加: パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、クローン病、多発性硬化症、膠原病など、自己免疫疾患も1970年代以降に急増しており、コンビニエンスストアや冷凍食品の増加とほぼ比例しています。
具体的な食品添加物の例と、その危険性は以下の通りです。
- カラメル色素: 分類1〜4があり、特にタイプ4は硫酸化合物やアルカリ化合物を使って人工的に酸化させて作られ、非常に強い発がん性があります。表示義務はあっても、どのタイプが使われているかは不明な場合が多いです。
- 果糖ブドウ糖液糖: 清涼飲料水のほとんど全てに使用されており、体内の様々な組織を糖化によって破壊する危険性があります。
- 亜硝酸カリウム/ナトリウム: ハム、ベーコン、ソーセージ、タラコなどの発色剤や保存料として使用されます。これらが胃液と反応するとニトロソアミンという強力な発がん性物質に変化し、胃がんの原因となります。
- タンパク加水分解物: いわゆる「うま味調味料」に含まれるアミノ酸等の一部で、レンダリング(動物の使えない部分や廃棄物、糞便など)から作られている可能性があります。食品添加物を用いて無臭化されます。
- トランス脂肪酸/水素添加油脂: マーガリンやショートニングの原料であり、植物油を水素添加して固めたものです。これは「植物性のプラスチックの塊」と表現され、体内に蓄積されます。女の子の子宮内膜や男の子の前立腺など、特に成長期の臓器に悪影響を及ぼし、重い生理痛や生理不順、前立腺疾患の原因となる可能性があります。
- 人工甘味料(例:アスパルテーム): カロリーゼロと表示されていても、長期間摂取すると味覚が麻痺し、インスリン抵抗性を引き起こし、最終的に血糖値を上昇させる可能性があります。WHOも発がん性の可能性を指摘しており、人工甘味料とがんの関連性を示す論文は増加傾向にあります。
- 増粘多糖類: 豆乳やグミ、菓子パン、麺類などにほぼ100%含まれており、食品の食感や舌触りを調節し、とろみをつける目的で使用されます。法律上は食品添加物として表示義務がない場合が多く、「無調整」と表示されていても実際には添加物まみれであることがあります。
- 合成着色料: 赤色3号、赤色104号、赤色105号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号、青色2号、緑色3号など多岐にわたり、発がん性の疑いがあり、多くの国で使用が禁止されていますが、日本では依然として許可されているものがあります。
- 精神疾患への影響: 植物油やトランス脂肪酸の過剰摂取は、腸内環境を悪化させ、脳の慢性炎症(ニューロインフラメーション)を誘発します。これにより、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の生成に影響を与え、うつ病、パニック障害、適応障害などのリスクを高めます。
〈「キャリーオーバー」という抜け道〉
食品添加物の危険性をさらに見えにくくしているのが、日本独自の「キャリーオーバー」という法律上の抜け道です。
- 仕組み: 原材料の製造・加工過程で使用された添加物が、最終製品にはごく微量で効果を発揮しない場合、表示が免除されるというルールです。
- 実態: 例えば、ボイルエッグ、食パン、マーガリン、マヨネーズそれぞれに法律上限まで添加物が含まれていても、それらを組み合わせて卵サンドを作ると、最終製品の「卵サンド」としては以前の添加物がカウントされず、新たに卵サンドに許可された添加物を加えることができます。これにより、表示上は「無添加」であっても、実際には複数の工程で大量の添加物が使用されている「添加物山盛り食品」が流通しているのが実態です。コンビニ弁当のハンバーグや漬物なども同様の状況です。
〈食品添加物の安全性試験の限界〉
食品添加物は、毒性試験(28日間、90日間、1年間反復投与毒性、繁殖、催奇形性、発がん性、変異原性試験など)を経て認可されます。しかし、これらの試験には限界があります。
- 試験期間の短さ: ラットの生涯は通常2年半ですが、発がん性試験でも最長2年半です。人間のがんは発症までに15年もの期間を要することがあり、短期間の動物実験では見過ごされる長期的な影響がある可能性があります。
- 平均摂取量の問題: 試験では平均的な摂取量を基準としますが、実際には高頻度で摂取する人(ヘビーユーザー)がいるため、その影響が十分に考慮されないという問題も指摘されています。
〈私たちにできること:加工食品を避け、食育を実践する〉
これらの食品添加物の危険性から身を守るためには、私たち自身の意識と行動を変えることが不可欠です。
- 「四毒」の排除を最優先に: 小麦、植物油、乳製品、甘いものの摂取を極力控えることが、健康改善への最も効果的な第一歩です。これにより、むくみの解消、肌の改善、アレルギー症状の緩和、精神状態の安定など、目に見える変化が期待できます。
- 生鮮食品中心の食生活: コンビニエンスストアの食品、インスタント食品、ファストフード、レトルト食品、缶詰といった「超加工食品」は、多くの食品添加物を含んでいるため、可能な限り避けるべきです。魚や肉、野菜などの生鮮食品を自分で調理することが、最も安全で健康的な選択です。
- 表示を鵜呑みにしない: 「無添加」や「成分無調整」といった表示があっても、キャリーオーバーの仕組みにより、実際には添加物が含まれている可能性があるため、安易に信用しないことが重要です。
- 食育の重要性: 子どもたちの健康を守るためには、幼少期からの食育が極めて重要です。加工食品を与え続けることは、将来の病気のリスクを高めます。
私たちの体は、食べたものでできています。目先の「美味しい」「安い」「便利」に惑わされず、自らの健康と将来の世代の幸福のために、賢明な食の選択をすることが求められています.